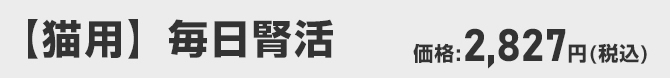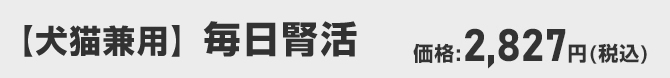猫の停留睾丸について知りましょう
どこからみても元気いっぱいなねこちゃん、でも異常があるの?これって大丈夫??
安心してこれからの毎日を楽しめるよう、具体的にどういう異常なのか、どうすればいいのか、一つずつお話していきますね。

そのねこちゃんが新しい環境で健やかに生活できるよう、飼い主さんにお渡しする前には健康チェックが行われます。その中のひとつにオスであればかならず、「睾丸」の確認があります。そこに異常があると「停留睾丸」となるのです。
陰睾丸、潜在精巣、停留精巣、停滞精巣、片タマ、片キンなどさまざまな表現があります。
どういう病気なの?
精巣は精子が作られる生殖器のひとつで、お母さんのお腹にいる胎児の時はまだ精巣が体内にあります。
生後1カ月ほどたつとオスのホルモンの影響をうけ、精巣が体内から正しい位置である陰嚢に向かって降りていきます。
この働きは個体差はありますが、だいたい2カ月ほどで完了し、精巣は陰嚢のなかにきちんとおさまり睾丸が2つ確認できるようになるのです。
この精巣下降期を過ぎても睾丸が確認できない状態を、停留睾丸と診断し、どこで精巣の下降が止まっているかで2つに分類されます。
・腹腔内陰睾
お腹の中で下降が止まってしまっている、触診では存在が不明で、エコーや腹腔鏡で確認ができる
・皮下陰睾
精巣がお腹からは脱出し、皮膚の下にある鼠径管を通って陰嚢に加工する途中で止まってしまっている、鼠蹊部の触診で確認できる
この異常は犬ではそうめずらしくはない状態ですが、猫ではまれで、どちらのタイプが多くみられるかなどまだ不明な点も多くあります。

だいじょうぶなの?
陰嚢内に下降していない精巣は、精子が体温の影響を受けやすくなるため、正常な性的機能が維持されず、不妊の原因となる可能性があります。
お腹の中は皮下よりもさらに高温となるため、この傾向は腹腔内陰睾でより明らかとなります。
しかしオスのホルモンは高体温でも正常に分泌されるため、メスを求める性欲に大きな差は見られません。
情報量が圧倒的に少ない猫の場合、これからわかってくることも多くありますが、少なくとも正常ではない状態に長く置かれることが何らかのリスクになる可能性は十分に考えられます。

どうすればいいの?
犬では遺伝的原因が強いと考えられているため、この異常をもつオスを交配させること自体が勧められていません。停留睾丸のオスを交配させれば、そのこどももやはり停留睾丸になる、というように癌リスクの高い異常が続いていってしまうかです。
猫の場合はまだそのあたり明らかにはなっていませんが、犬に比べると下腹部の脂肪が多く、触診による腫瘍の確認がしづらいため、まれではありますが発見時にはかなり悪性度が強く、肝臓や消化管などへの転移にすすんでしまっていることもある腫瘍です。
そうなりますと、やはりとるべき方法は手術による停留睾丸の摘出です。
・腹腔内陰睾
開腹し、体内にある精巣を摘出します。
最近犬では内視鏡のひとつである腹腔鏡をつかった手術もあり、手術の侵襲度や時間が大幅に減少することで術後の回復もかなり早くなりました。猫にも今後の適応範囲の拡大が期待されます。
・皮下陰睾
鼠径部を圧迫し、摘出に適した部位で皮膚を切開し精巣を摘出します。場所によっては通常の去勢手術とほぼ変わらない術式で行うことができる場合もあります。
何に気をつけるべき?
停留睾丸の治療は早期発見、早期摘出が基本です。
愛猫を迎えた時にすでにわかっているときは、新しい生活に慣れたらかかりつけの病院と摘出手術の相談をしましょう。
なんらかの事情ですぐに手術が難しい場合、または保護したり譲り受けた猫で停留睾丸がどうかの判断がつきずらいときは病院ではもちろんのこと、お家でも定期的にチェックしましょう。
・陰嚢内に睾丸が2つあるかどうか
・2つない場合、後足のつけね~内股である鼠径部にふくらみがあるかどうか
・ふくらみがわからない場合、またはぽっちゃりめで下腹部の確認がむずかしい場合はかならず動物病院で確認しましょう
・すぐの摘出を行わない場合、その大きさ、硬さ、触って痛みがないかなどを確認

<おすすめ動画>

<関連記事>
猫の皮膚病を防ぐためのポイントは?猫の皮膚病を予防するためのポイントを紹介します。 猫がなりやすい皮膚病も一緒に紹介します。

<関連記事>
猫の目ヤニがひどい時に考えられる原因は?目のケアのポイント愛猫の健康を守りながら、快適な生活をしてもらうための環境づくりは飼い主さんの役割ですが、ある程度の怪我や病気は避けられないものです。 中でも愛猫の目から目ヤニがでていたり、痒がっていると心配になりますよね。 愛猫の目ヤニがひどいときに考えられる原因について紹介します。

<関連記事>
猫も熱中症になる?!夏になったら要注意、飼い主さんができること【概要】 「熱中症」という言葉はみなさんご存じですよね、しかしそれは人やワンちゃんに限るものと思われてはいませんか? 実は猫も熱中症にかかるんです、しかも人や犬と同じようになってしまうと非常に重症化しやすく緊急で治療が必要になってしまうこともあるんです。 残念なことに最悪命を落としてしまうことがあるだけでなく、その後の身体の状態に影響を与えかねない熱中症、ぜひ正しい知識を身につけて猫ちゃんを守ってあげてください。